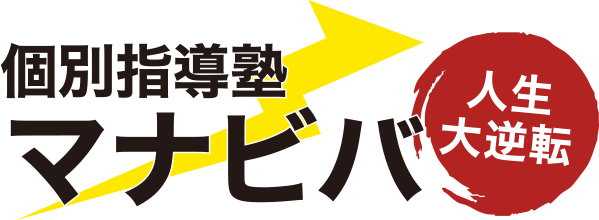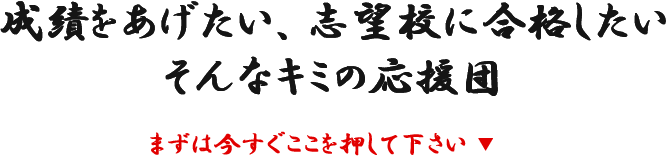自分は確かに文系だけど、どの学部に行けばいいかわからない・・・
そんな悩みを抱える高校生は、実は大学選びよりも学部選びが深刻だったりすることがあります。
今回は、「文系で役に立つ学部」を紹介します。学部選びの参考にお読みください!

文系で役に立つ学部6選
<経済学部>
「経済学部」は、社会全体の経済の仕組みを学ぶ学部です。
経済活動と一口に言っても、国や地域の政治から、企業、あるいは消費者の経済活動まで幅広くあります。そういう社会全体の経済活動を学ぶのが「経済学部」です。理論的に学ぶ要素が強い学問です。
社会の生産、分配、消費に関する活動を「経済」と呼んでいますが、この「経済学部」ではお金を中心とした経済のメカニズムや経営について学ぶことが主な目的です。
大学では、マクロ経済学、ミクロ経済学、統計学、経営学、経済史まで幅広く学べます。
経済についての知識があると、金融業や商業などの専門的な職業だけでなく、お金の流れを理解していると有利なため、ほぼ世の中の経済活動に関わってくるすべてのものに関係のある学部です。
「経済学部」出身の人は、
- マーケティング職
- フィナンシャルプランナー
- 証券アナリスト
- 銀行、保険、金融業
などの仕事がオススメです。
<経営学部・商学部>
「経営学部」は、企業や組織の運営の関わる管理と運営方法、その仕組みなどを学ぶ学部です。
経済学部が経済活動についてであるのに対し、「経営学部」は経済を動かす組織や企業の運営について研究するのが中心です。
「商学部」は、商売を学ぶ学部です。企業が組み上げた物流やお金の流れなど、企業と消費者の関係性を勉強します。
文部科学省の分類では、商学は経済学や経営学と同じ区分になります。その中で、社会生活に実践的に活用できる学問という所が大きな特徴です。
経済学部や経営学部が経済活動全般や企業の運営を勉強するのに対し、この「商学部」では企業が扱う「商い」を勉強します。その点でよく「実学」とも言われます。
お金の流れの専門的な知識や技術が学べるため、金融業や商業などでの採用確率は高くなります。
「経営学部」「商学部」出身の人は、
- 公認会計士
- 税理士
- 企業の財務、経理
- 店舗の運営
などの仕事がオススメです。
<法学部>
「法学部」は、法律を学ぶ学部です。
法律の専門的な知識を学べるため、弁護士、司法書士、行政書士、検察官、裁判に関わる仕事など、法律の知識が求められる職業に直結します。
例えば消費者に商品やサービスを提供するとき、会社が役所と様々な手続きをするとき、業者と商品の取引を行うとき、などで法律の知識は必要です。
法律の運用方法を学ぶ解釈論や、新しく法律を作るための立法論を勉強し、最終的に社会に生かせるような法の知識の使い手を目標とします。
法律と関係ない業界や職種はまず皆無です。全ての業界や職種において、法律に強い人は企業から歓迎されます。
「法学部」出身の人は、
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 検察官
- 公務員
などの仕事がオススメです。
<外国語学部・国際教養学部>
「外国語学部」「国際教養学部」は、日本語以外の言語を使う学部です。
どちらの学部も留学制度が充実しているため、留学を義務付けている大学も増えています。また、海外から留学生を招き入れ、学内においても外国語を実践できるような大学が多数あります。
実際には多言語の習得は簡単ではありません。グローバル化が進む中、人材は常に不足しています。外国語を話せれば、就職活動において非常に優位に立てます。
「外国語学部」「国際教養学部」出身の人は、
- 外資系企業
- 貿易会社
- 通訳ガイド、旅行業
- 翻訳業
- 英語スクール講師
などの仕事がオススメです。
<教育学部>
「教育学部」は、教育をについて学ぶ学部です。
「教育学部」は、大学で教員免許を取得できます。教員免許は、学校の教諭になるために必要な資格です。
「教育学部」の卒業者は、もし学校の先生に就かなくても企業で新人や若い部下など後輩の教育にあたる仕事も可能です。人を教え育てる能力は幅広い場面で役立ちます。
「教育学部」出身の人は、
- 学校教員
- 図書館司書
- 学芸員
- 企業の研修業務
などの仕事がオススメです。
<社会学部・人文学部>
「社会学部」「人文学部」は、人間が営む社会の仕組みや人が生活しやすい社会づくりを学びます。
「社会学部」「人文学部」は専攻が細分化されています。社会学、心理学、メディア研究、哲学、文化、歴史など、専攻が分かれている大学が多数あります。
社会や個人が抱える問題や人間が生きてきた過程を様々な視点で観察し、研究することが目的です。言い換えると「人間」そのものや「人間の活動によって生み出される社会」が研究対象となります。
「社会学部」「人文学部」で知識と教養を身につけた後に自分自身が社会へとデますが、情報通信業、製造業、出版業、学校関係、金融・保険業、サービス業、福祉など多岐に渡ります。
「社会学部」「人文学部」出身の人は、
- 記者、ライター
- 編集者、Webディレクター
- 出版、放送、校正
- 福祉
などの仕事がオススメです。

この学部ってホントに文系!?
文系に属してはいますが、学習内容を見ると「ホントに文系なの!?」と思ってしまう学部もあります。
<心理学部>
「心理学部」では、人間の心について実験や調査などを通じて科学的に研究する学部です。大学の学部・学科の編成上は文系の学部に分類されていますが、心理学は精神医学と同様の医療系と考えれば理系色が強い学部といえます。
特に、大学院まで進んで臨床心理士の資格を取得するなら、実験や統計字は絶対に落とせません。理系の数式や実験などが苦手な人にとっては厳しいと感じる可能性があります。
卒業後は心理カウンセラー以外にも、福祉・医療現場の職員や一般企業の人事としても専門性が活かせます。
心理カウンセラーとして知られる「臨床心理士」は大学院への進学が必須ですが、国家資格ではなく民間資格です。また、公的資格だった「産業カウンセラー」も現在は民間資格になっています。
2017年から施行された新しい国家資格で「公認心理師」があります。
<経済学部・経営学部・商学部>
先述した「経済学部」「経営学部」「商学部」は文系ですが、実質的に理系の要素も入る学問に取り組みます。
わかりやすい事例は公認会計士や税理士の仕事です。多くの人がご承知のように、税理士は会計学を学ばなければなりません。当然に数式や計算が必要な学問です。
数式や計算が必要、と理解していも税理士や公認会計士は実際に文系に分類されてしまっています。ガチガチの文系の人で数学が苦手なら、税理士や公認会計士を目指すのは大変です。
数学に関する理解と応用を身につけることが求められるので、文系だからといって数学や理科と関わらなくていい、ということになりません。その点をよく理解しましょう。

文系の学部の受験科目は?
最後に、文系の学部の受験科目を見てみましょう。
<入試科目は何が必要か>
国公立大学の場合
国立大学と公立大学を受験する場合、必ず課されるのが「大学入学共通テスト」(略称は共通テスト)です。
科目は2023年時点では基本的に5教科7科目の大学が大多数ですが、2025年から「情報」が試験科目に追加されて6教科8科目となります。
解答用紙はマークシート式です。
国公立大学では、先にこの「共通テスト」を実施し、それを自己採点します。その点数を見て、出願校を正式に決定します。そして志望校に願書を提出し、改めて「二次試験」が実施されます。
二次試験は、共通テストより難しい問題が出題されるのが一般的で、大抵の受験生は「二次試験は一次試験より難しい」と見ています。
文系の学部では「外国語、数学、国語、地歴・公民」から2~3科目が主流ですが、一部の難関大学は4科目で実施するところもあります。
それぞれの大学で別々の試験が作られるため、科目数だけでなく出題の内容を知っておかないと準備もうまく行きません。過去問などで傾向と対策をよく研究することが大切です。
私立大学の場合
私立大学は、基本的に外国語、国語、社会の3科目を課す大学・学部が一般的です。
近年は受験生にチャンスを広げるため外国語に国語または社会、など2科目だけで受験できる方式や1科目だけで高得点を狙う方式の試験も増えてきています。
受験科目の堅実な選び方としては、人文学部であれば歴史、法学部や経済学部であれば政治経済のように、大学の学部で学ぶ内容と関係の深い科目という方法があります。
大学に行って困らないためにも、法律や行政を専攻するのに日本史しかやっていないとなると、入学後に1年生の一般教養課程の基礎レベルの授業から苦戦することになります。
以上のことから、大学で学ぶ内容と関係の深い科目を選ぶことをオススメします。
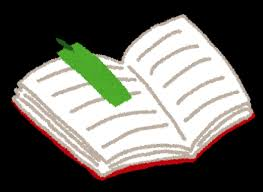
まとめ
今回は、「文系で役に立つ学部」を紹介しました。
入学した学部によって、卒業後の職業の候補が違ってきます。そこを忘れずに、興味のある学部を選んで勉学できれば後で困りません。
大学の学部で学んだ知識と教養を活かして卒業後は思い描く職業人として活躍できれば理想的です。
スタディサプリ
https://shingakunet.com/journal/column/20210415000002/
キャリアガーデン
https://careergarden.jp/department/
テレメール
https://telemail.jp/shingaku/gakumon/