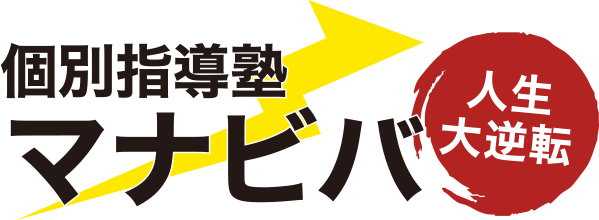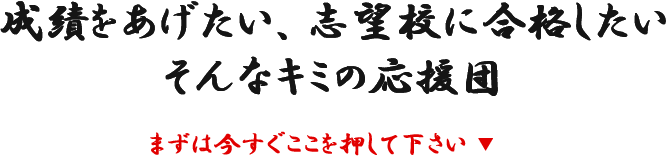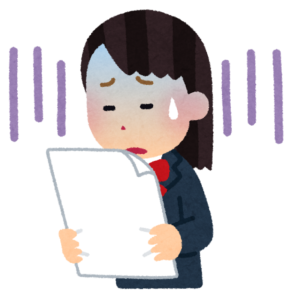
「勉強を頑張ったのに、なかなか点数が伸びない。」と悩んでいる人はいませんか?もしかすると、「ケアレスミス」が原因かもしれません。
しかし、ケアレスミスをなくそうと思っていても、ケアレスミスそのもののことを理解していないと、気を付けようがありません。
今回は、ケアレスミスの原因やよくあるケアレスミスについて解説していきます。
こんな人は要注意!よくあるケアレスミスとは?
ケアレスミスと一口に言っても、その種類や原因は様々です。間違った原因を分析することで、次に向けての改善策を考えることができます。
では、ケアレスミスとはどのようなものなのでしょうか?基本的には「本当は正解できるのに、勘違いやうっかりで間違ってしまったもの」をケアレスミスと言います。
「自分はケアレスミスはなかった。」と主張する人もいるかもしれません。しかし、以下のようなミスが続いていることはありませんか?教科ごとに自分のテストを振り返って確認してみましょう。
国語
- 漢字の書き間違え(同音異義語など)
- 漢字の形(トメハネや点の有無)や送り仮名のミス
- 誤字脱字
- 必要文字数を満たしていない記述問題
- 「傍線部を現代語訳しなさい」という問題に傍線部外も訳してしまった。
- 選択問題で合っているものを選ぶと思っていたら間違っているものを選ぶ問題だった。
- 漢字の読み方を「カタカナ」で書きなさいという問題にひらがなで回答してしまった。
数学
- 式は合っていたのに、計算を間違えた。
- 筆算で繰り上がりをしなかった。
- 計算して出てきた答えを約分していなかった。
- 数学の三角比の問題で、図形に数値を書き写す時に写し間違えをしたため解答できなかった。
- +と-を書き間違えて、-だったのを+にしていた。
- 数学の計算問題で( )を外すとき+と-を逆にして解答した。
- 計算ミス、移項時の符号変え忘れ。
- 暗算による計算ミス。
- X(エックス)と×(かける)の見間違え。
- 問題文は「X(エックス)」だったのに「a」で解き進めそのまま解答。
社会
- 人名や出来事の漢字の書き間違え。
- 年号の数字が一部ひっくり返る。
- 国名が正しく書けていなかった。
- ひらがなで書くべき指定を漢字で書く。
- 選択問題で合っているものを選ぶと思っていたら間違っているものを選ぶ問題だった。
理科
- 選択問題で合っているものを選ぶと思っていたら間違っているものを選ぶ問題だった。
- 物質Bに対して正しいグラフを選ぶ化学の問題で、物質Aに対しての正しいグラフを選択してしまった。
- 単位のつけ忘れ、書き間違い
- グラフの縦軸と横軸の読み間違え
- グラフやデータの持つ意味を勘違い
英語
- 「傍線部を現代語訳しなさい」という問題に傍線部外も訳してしまった。
- 文頭を大文字にしていない
- ピリオド・クエスチョンマークの付け忘れ
- 三単現の–s(-es)を忘れる、不要に残す
- 動詞の時制ミス(過去形、現在形、未来系、進行形など)
- does/didの文中で動詞を原型にしていない
- 単純なスペルミス
このようなミスが続いている人は、ケアレスミスをしやすい傾向にあると言えます。対策をして、次のテストからはケアレスミスをしないように気を付けましょう。
どうしてケアレスミスは起こるの?ケアレスミスの原因を解説!
では、このようなケアレスミスは何が原因で起こるのでしょうか?ケアレスミスの原因は大きく分けると以下の4つです。
- 注意力散漫によるもの
- 体調不良によるもの
- うっかりしてしまったことによるもの
- 勘違い、思い込みによるもの
慣れや気のゆるみから確認を忘れたり怠ったりする、または、過信や慢心から脳が「正しい」と判断してしまうことからケアレスミスが起こります。
また、緊張からケアレスミスをすることもあります。
そのため、冷静に見直しをすることでミスに気づくことができます。 しかし、しっかり見直しをしようと意識してもミスを見逃したり、見直しをすること自体が頭からなくなったりするものです。
「気を付けよう。」という精神論ではなく、具体的な行動で対策をしていく必要があります。
このうち、体調が悪かったりや注意力が散漫な状態になっているなど、体が原因のことについては対策がしやすいです。しかし、勘違いや思い込み、うっかりというのは、考え方の癖が原因となっている場合があります。この場合は、無意識のうちに身に付いてしまっているものなので、なかなかすぐには直りません。
ケアレスミスの原因をしっかりと分析することも、対策につながります。
まとめ
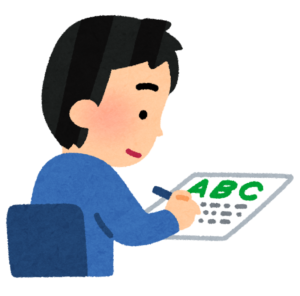
ケアレスミスをしないようにするためには、「忘れないように頑張る。」という精神論では解決できません。メモを書いたり、時間を考えたりするなど、具体的な対策をとることが必要です。
また、テストの時にこのような対策をとろうとしても、緊張から忘れてしまうことがあります。
普段の勉強で問題を解くときや、テストの練習をするときなどから、同じ対策をとりましょう。そうすることで、ケアレスミス対策が習慣化し、意識しなくても自然にできるようになります。
以下のコラムでは、ケアレスミスの具体的な対策について紹介しています。今回紹介したケアレスミスをよくしてしまう人は、どのように対策したらいいか、一緒に見ていきましょう!
ケアレスミスをなくすことで、勉強した力を100%テストで発揮できるようにしましょう。