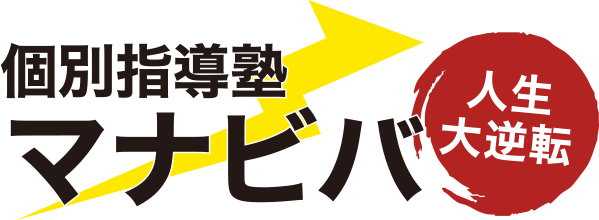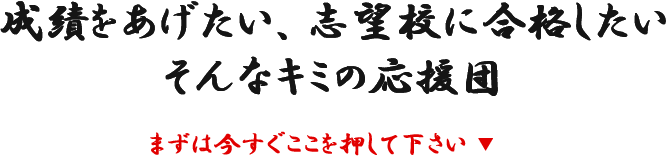中学1年生の理科では、「身の回りの物質-光」という単元を学習します。
そこでこの記事では、この単元が苦手という中学生やそして中学生に勉強を教える親御さんのために抑えておくべき重要なポイントをわかりやすくまとめたので参考にしてください。
中学1年生の理科では、「身の回りの物質-光」という単元を学習します。
そこでこの記事では、この単元が苦手という中学生やそして中学生に勉強を教える親御さんのために抑えておくべき重要なポイントをわかりやすくまとめたので参考にしてください。
まずは基礎!光源・光の反射・光の直進を理解しよう
 光の進み方を学習するにあたって、まずは「光源」「光の反射」「光の直進」という言葉を抑えましょう。
それでは一つずつ解説するので、覚えておきましょう。
光の進み方を学習するにあたって、まずは「光源」「光の反射」「光の直進」という言葉を抑えましょう。
それでは一つずつ解説するので、覚えておきましょう。
光源とは
光源とは、自分から光を発している物体のことです。 身近な例では、太陽とか、蛍光灯などがあります。光の直進とは
光の直進とは、光源から発射された光がまっすぐに進むことです。 曲がったりすることはなくまっすぐ進みます。光の反射とは
光の反射とは、光が物体の表面に当たってはね返えることです。 光源から発せられた光が、物体の表面に反射することで、私たちは光源ではないものを視認できています。光の反射の法則を解説
 光の反射の法則とは、鏡に光を当てたとき、入射角と反射角が等しくなるっていう法則です。
光の反射の法則では、「入射角」と「反射角」が基礎となるのでしっかり理解しましょう。
光の反射の法則とは、鏡に光を当てたとき、入射角と反射角が等しくなるっていう法則です。
光の反射の法則では、「入射角」と「反射角」が基礎となるのでしっかり理解しましょう。
入射角とは
入射角とは、鏡に光を当てたときに、「入ってくる光の道筋」と「鏡に垂直な線」がつくる角度のことです。 光線がある物体に当たることを「入射」っていうから、入射(光源から鏡へ当たるとき)するときの、鏡に対する角度を「入射角」と呼んでいます。反射角とは
反射角とは、「反射した光の道筋」と「鏡に対して垂直な直線」との角度のことです。 光の鏡に対する角度っていうのは同じなんだけど、入ってくる光との角度のなのか、反射する光との角度なのかが異なっています。光の反射の法則について
改めて光の反射の法則とは、鏡に光を当てたとき、入射角=反射角になることです。 たとえば、鏡に光を当てたとき、入射角が40度だった場合、光の反射の法則より、反射角も同じ40度になります。乱反射とは
続いて、乱反射についてみていきましょう。 乱反射とは、表面がデコボコしている物体に光を当てたときに、いろんな方向に反射することです。 一つの方向からの光源しかなくても、表面がデコボコしているものに光があたっている時は、いろんな方向に光が進んでいきます。 先述した「光の反射の法則」がないもののように見えますが、光をいろんな方向から受けていることによってひとつひとつの光の道筋が「光の反射の法則」に従ってしっかりと反射しているので法則に従った反射です。全反射とは
続いて全反射について解説します。 全反射とは、入射角を大きくしていくと、光が屈折しないで反射してしまう現象のことです。 つまり透明な物体から空気中に光が飛び出さずに透明な物体の方向へ跳ね返されてしまうという反射の一つです。 光の屈折の法則によると、透明な物体から空気へ光が通るとき、屈折角は入射角よりも大きいと先ほど説明しましたが、入射角をどんどん大きくして、徐々に90度に近づいてくると、入射角よりも屈折角の方が先に90度に達してしまいます。 つまり、屈折角が90度ってことは、透明な物体と空気の境界面と平行に光が進んでいくことになってしまい、それよりも入射角を大きくして屈折角が90度より大きくなると、光は境界面を飛び越えて空気へいけないという仕組みです。 全反射が起こるのは、水やガラスなどの透明な物体から、空気中へ光が通るときです。その逆の、空気から透明な物体へ光が入ってくるときは全反射は起きないので注意です。 一度全反射になると、光の道筋には「光の反射の法則」が適用され、入射角と反射角が等しくなり、屈折角じゃなくて名前が反射角になってる点に注意しましょう。光の屈折の法則を解説
 光の屈折の法則とは、光が空気中から透明な物体に入るとき、入射角の方が屈折角より大きくなり、透明な物体から空気中に光が入ってくるとき、屈折角の方が入射角より大きくなるというものです。
それでは詳しくみていきましょう。
光の屈折の法則とは、光が空気中から透明な物体に入るとき、入射角の方が屈折角より大きくなり、透明な物体から空気中に光が入ってくるとき、屈折角の方が入射角より大きくなるというものです。
それでは詳しくみていきましょう。
光の屈折の法則の入射角・屈折角の意味
まずは、入射角と屈折角という言葉を解説していきます。 これらの2つの言葉はすべて、空気中から透明な物体へ光をあててみたり、透明な物体から空気中へ光を当ててみたりする場合に使われる言葉です。入射角とは
入射角とは、入ってくる光の道筋と境界面に垂直な線との角度のことです。 ここでいう「境界面」とは、空気または透明な物体の境目のことです。屈折角とは
屈折角とは、出ていくときの光の道筋と境界面に垂直な線との角度のことです。 出ていくときの道筋はまっすぐではなく屈折するから、屈折角と呼ばれています。光の屈折の法則について
光の屈折の法則とは、- 光が空気中から透明な物体に入るとき、入射角の方が屈折角より大きくなる。
- 透明な物体から空気中に光が入ってくるとき、屈折角の方が入射角より大きくなる。
「空気 → 透明な物体」の場合
まず、空気中から透明な物体に光が入るときのパターンをみてみましょう。 このとき、光の屈折の法則によると、入射角の方が屈折角より大きくなります。入射角>屈折角
「空気 ← 透明な物体」の場合
今度は、透明な物体から空気中に光が入ってくるパターンをみてみましょう。 この場合は、屈折角の方が入射角より大きくなります。入射角 < 屈折角
つまり、空気中から透明な物体に入れる、透明な物体から空気中に入れた光は、境界面で曲がって光の道筋が変化するということが屈折の法則です。