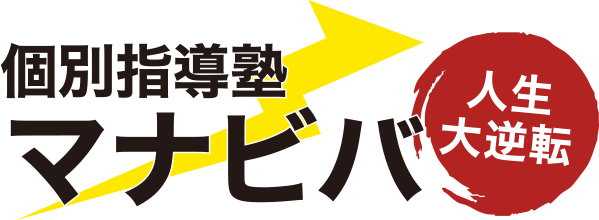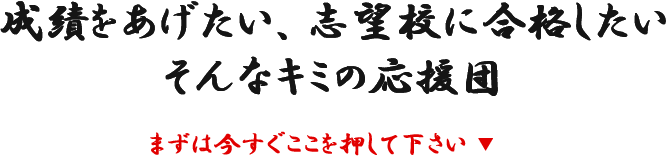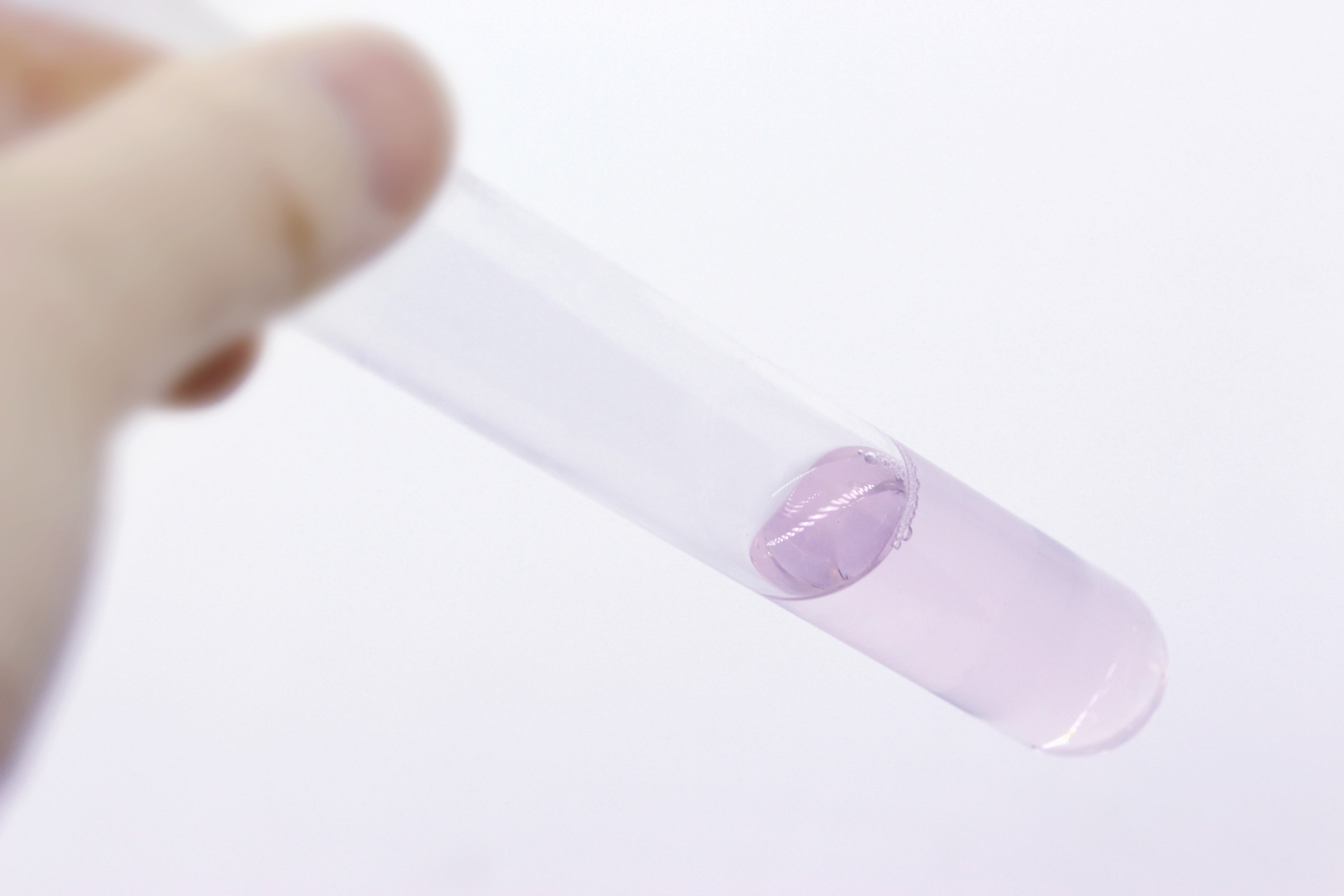 中学1年生の理科では、「身の回りの物質-水溶液」という単元を学習します。
中学1年生の理科では、「身の回りの物質-水溶液」という単元を学習します。
そこでこの記事では、この単元が苦手という中学生やそして中学生に勉強を教える親御さんのために抑えておくべき重要なポイントをわかりやすくまとめたので参考にしてください。
溶質・溶媒・溶液・水溶液の違いとは?
 溶質・溶媒・溶液・水溶液の違いを説明するにあたって、水に砂糖を溶かして砂糖水を作ることをイメージしながら行っていきます。
それでは一つずつみていきましょう。
溶質・溶媒・溶液・水溶液の違いを説明するにあたって、水に砂糖を溶かして砂糖水を作ることをイメージしながら行っていきます。
それでは一つずつみていきましょう。
溶質とは
溶質とは、溶かす物質のことです。 イメージしてもらった砂糖水を作る場合は、砂糖が溶質です。溶媒とは
溶媒とは、溶けるのを媒介する物質のことです。 「媒介する」ってつまり、橋渡しをするってことで、砂糖水の場合は、水が溶媒となります。 溶質を溶かすには、絶対に媒介となる「溶媒」が必要ということを覚えましょう。溶液とは
溶液とは、溶質が溶けてできた液体全体のことを指します。 砂糖水の場合は、混ざって出来上がった砂糖水が溶液ということです。水溶液とは
水溶液(すいようえき)とは、水でに溶けてできた液体のことです。 砂糖水は、溶媒が「水」だからもちろん水溶液となります。密度の求め方
密度とは、単位体積あたりの質量のことです。 噛み砕いて説明すると、ある体積あたり(例えば1cm³)あたり、そいつが何gというのかを表した数値になります。 密度の出し方は次の公式で計算することができます。密度 = 質量 ÷ 体積
つまり、「重さ」を「大きさ」で割ってあげるだけなので簡単に求めることができます。質量パーセント濃度の求め方
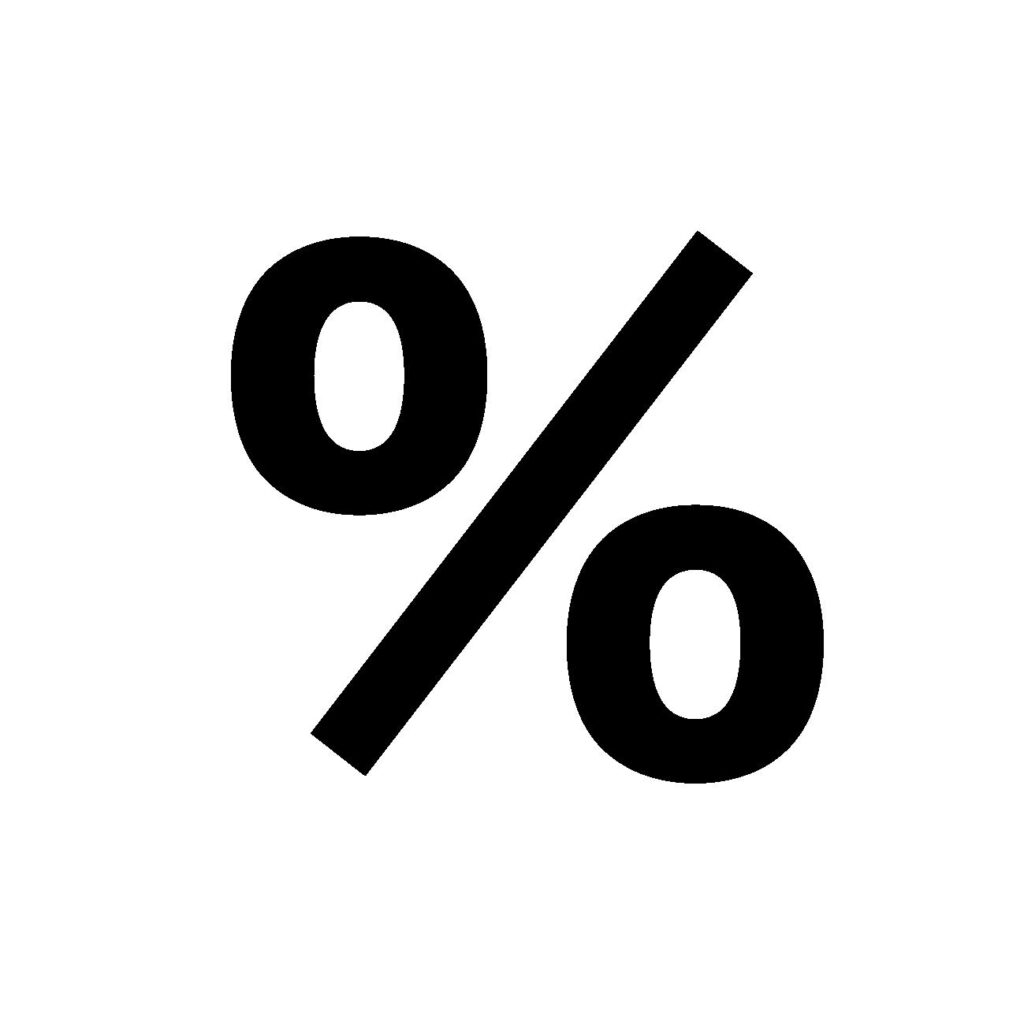 質量パーセント濃度の求め方の公式は以下の通りです。
質量パーセント濃度の求め方の公式は以下の通りです。
(質量パーセント濃度 [%] )= (溶質の質量)÷(溶液の質量)×100
「溶かす物質の重さ」を「溶けてできた液体の重さ」で割り、%にするために「100」をかければ良いです。 質量パーセント濃度とは、「溶かした物質の重さ」が「溶けてできた液体全体の重さ」のうちどくらいの割合を占めているかをパーセントで表したものとなります。 たとえば、とある食塩水の質量パーセント濃度が30%だとします。 この食塩水全体が100gだとしたら、この食塩水の中には、100gのうち30%は塩が入っているということになり、30gの塩が入ってることになります。質量パーセント濃度の求め方を「溶質」と「溶媒」だけで表した場合
これは、「溶液の質量」が「溶質」と「溶媒」の質量を足したものってことをつかって変形すると以下の通りの公式になります。 (質量パーセント濃度 [%] )= (溶質の質量)÷(溶質の質量 + 溶媒の質量)×100溶解度曲線と再結晶について
 まず「再結晶」とは、合成または抽出などによって得られた粗結晶(純度の低い結晶)をより良質で不純物の少ない結晶へと成長させるための操作のことです。
たとえば、物質AとBの混合物があったとして、ある動作をすると、物質Aだけ取り出すことができるということです。
中学校で勉強する理科では、「溶解度の差」を利用して、純度の高い結晶を取り出していくことができるということで、物質Aに、不純物の物質Bが混じっている場合、物質Aだけを取り出したいとき、再結晶を使うことで取り出すことができます。
まず「再結晶」とは、合成または抽出などによって得られた粗結晶(純度の低い結晶)をより良質で不純物の少ない結晶へと成長させるための操作のことです。
たとえば、物質AとBの混合物があったとして、ある動作をすると、物質Aだけ取り出すことができるということです。
中学校で勉強する理科では、「溶解度の差」を利用して、純度の高い結晶を取り出していくことができるということで、物質Aに、不純物の物質Bが混じっている場合、物質Aだけを取り出したいとき、再結晶を使うことで取り出すことができます。
まず混じった物質たちを水に溶かして、冷やして、溶解度を小さくすると、溶けきれなくなった物質Aが結晶で出てくる。 物質Bは物質の性質上、温度が下がってもまだ十分な溶解度を持つことができた上記例のように、冷やすと、溶けきれなくなった、物質A(純粋)が結晶として取り出すことができるというわけです。
飽和水溶液、溶解度、溶解度曲線とは
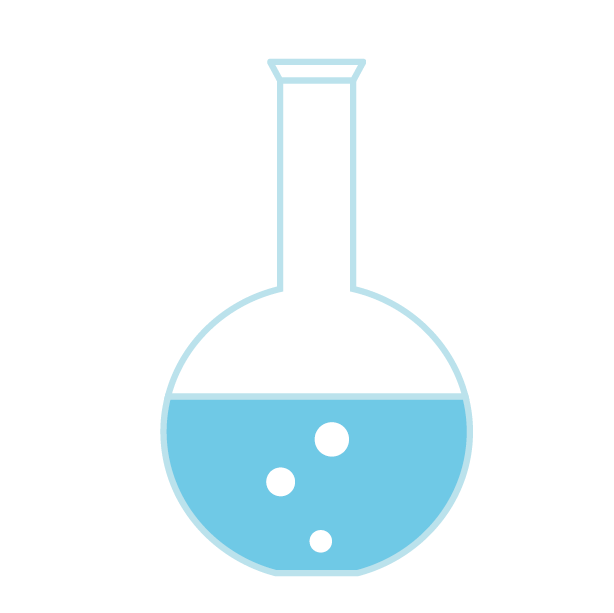 飽和水溶液、溶解度、溶解度曲線は関連した言葉です。
それぞれどういった意味があるのかしっかり覚えておきましょう。
飽和水溶液、溶解度、溶解度曲線は関連した言葉です。
それぞれどういった意味があるのかしっかり覚えておきましょう。
飽和水溶液とは
ある物質を水に溶かすとき、水は無限にその物質を溶けさせることはできず、水には物質を溶けさせることができる限界があります。 ある物質が水の限界まで溶けきった水溶液のことを、飽和水溶液って呼んでいます。 飽和水溶液にこれ以上その物質を加えてみても、その物質は溶けません。溶解度とは
飽和水溶液をつくるためにどれくらい物質を溶かしたのかを表したのが「溶解度」です。もっと具体的にいうと、ある物質を水100gにとかして飽和水溶液にした時のとかした物質の量になります たとえば、水100gに大量のミョウバンを入れてミョウバンの飽和水溶液を作った場合、ミョウバンを40g混ぜて飽和水溶液ができたました。 そうするとこのミョウバンの飽和水溶液の溶解度は40gになります。溶解度曲線とは
この溶解度というものは、温度によって変化する性質を持っています。 たとえば、40℃の時の溶解度が50gだったとしても、温度を上げて100℃にしたら溶解度が100gになる物質もあります。 この、水の温度によって溶解度が変化する様子をグラフにしたものを、溶解度曲線と呼ばれます。 この溶解度曲線というグラフは 縦軸:溶解度 [g] 横軸:水の温度 [℃] を撮ったもので、この溶解度曲線というグラフの読み取り方は簡単で、物質Aの30℃の溶解度を知りたいときは、30℃の時の溶解度を溶解度曲線から読み取れば良いだけです。純物質と混合物の違い
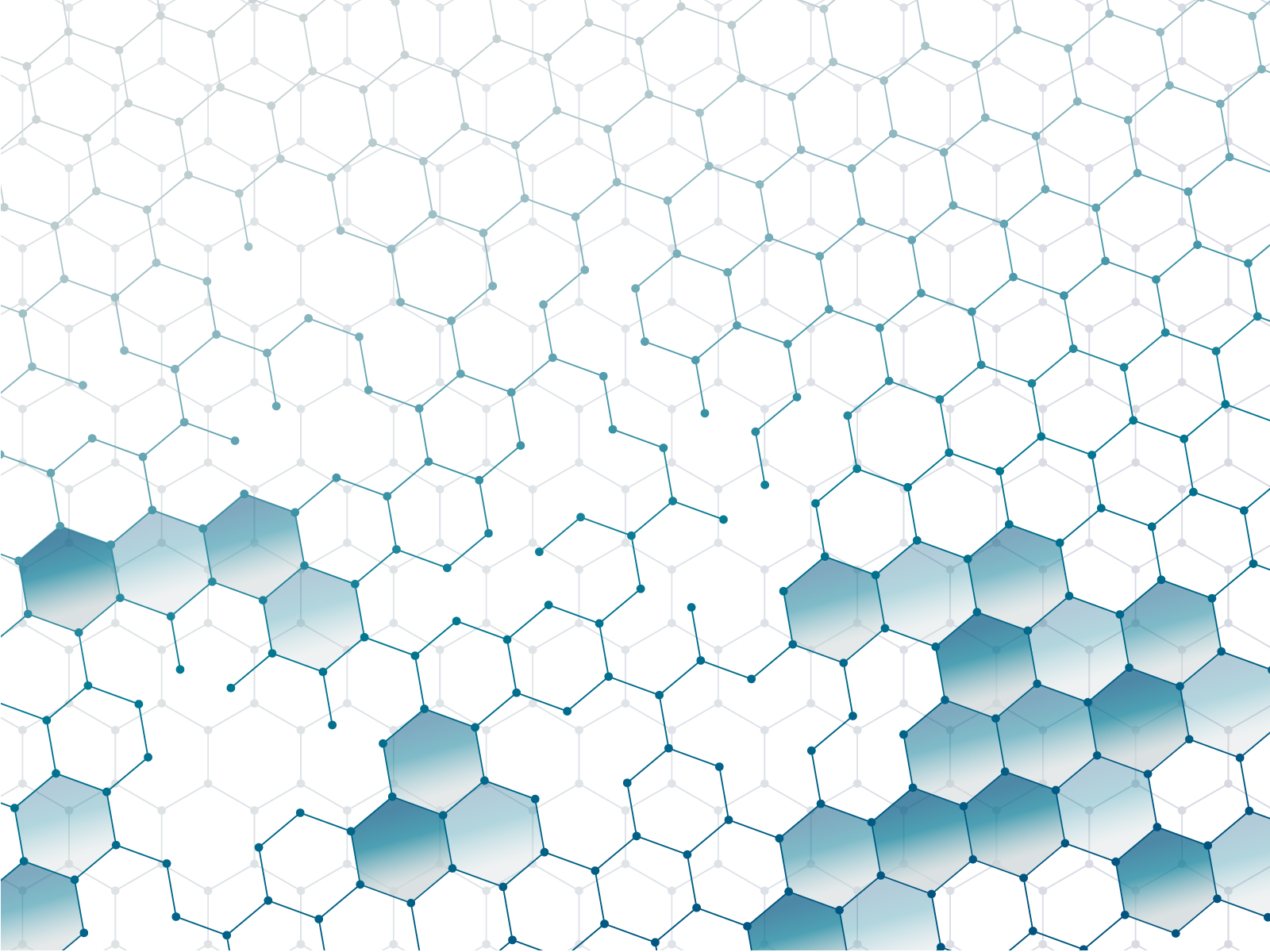 純物質と混合物の違いは、何種類のものでできているかという点です。
純物質と混合物の違いは、何種類のものでできているかという点です。
- 純物質:1種類の物質からできてるもの
- 混合物:2種類以上の物質からできてるもの