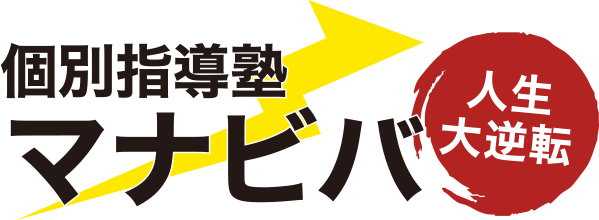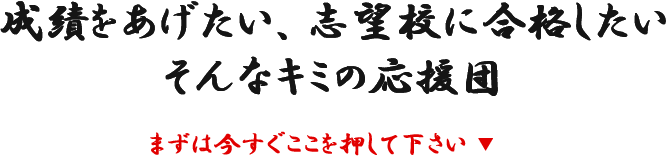入試対策
勉強の攻略法
受験勉強はいつから始める?
受験勉強はいつから始めるべきか?
受験勉強について考え始めるタイミングは人それぞれです。
例えば、中学入学した時点で憧れの高校があり、合格するためにはいつから勉強すれば良いのか、通塾はどうしようかと考える人。あるいは、部活中心の生活を送っており、部活引退を機に受験を意識し始める人。また、気づいたら時間が経っており、「あれ、受験勉強乗り遅れたかも…?」と焦って受験勉強し始める人。このようなそれぞれの人に共通して言えるのは、“意識し始めた瞬間に勉強し始めるのがいちばん効果的である”ということです。なぜなら、思い立ったこの瞬間が1番受験まで多くの時間が残っているからです。中学1年生でも、中学3年生でも、思い立ったこの瞬間にスタートすることが大切です。
1中学1年生から始める場合
中学1年生から高校受験への意識を持っている人は、部活動や遊びと両立しながら余裕を持って勉強を進めることができます。また、中学1年生からコツコツ受験勉強することができれば、難関校も目指すことができます!高校の選択肢が広がります!
勉強のポイントは、積み重ねが必要な英語・数学を中心に5科目の基礎固めをすることと、定期テストで好成績を取れるように自分に合った勉強方法を身につけることです。
-
① 英語と数学の基礎固め
英語と数学は最初の1年が特に大切な教科です。なぜかというと、英語も数学も知識と理解を積み重ねていく教科で、早くから基礎力が固まっていると、そのあとの学習がスムーズに進むためです。
逆にいうと、1度つまずきが出るとそのあとに習うものも理解できなくなって行き、やがて苦手教科になってしまいます。そのため、毎回の授業を確実に理解することが重要です。 -
② 定期テスト対策の勉強方法を身につける
公立高校の入試では内申点が大きく影響し、内申点は定期テストの結果でだいたい決まります。定期テストは手を抜けません。
中学1年生のうちに自分に合った勉強方法を身につけておけば3年間使える武器になり、内申点を上げる鍵にもなる。
テスト対策をしっかりしていたか否かがわかりやすい教科が理科・社会です。理科・社会は定期テストの時にしっかり暗記していると、3年生の総復習をする時にすっと内容を思い出すことができます。受験生になった時に楽するためにも、1年生のうちに勉強方法を身につけられるよう意識を高めましょう。
2中学2年生から始める場合
中学2年生は部活動や学校行事で重要な役割を担うようになり、とても忙しくなります。学校の勉強は中学1年生の時に比べて難易度が上がるだけでなく、スピードもアップします。
中学2年生から受験勉強を始める人は、「今習っている内容を100%理解すること」が重要です。さらに、志望校を具体的に持てるとモチベーションUPに繋がります。もし、志望校が難関校や倍率の高い高校であれば、今からもう一歩踏み込んだ学習を今から始められるので、合格へ一歩近くことができます。
-
① 今習っている内容を100%理解する
勉強の難易度が上がり、スピードアップする中学2年生の学習は決して油断できません。この時期から受験勉強を始めることはとても価値があると言えます。定期テストのためにも、受験勉強のためにもその都度学習内容を100%理解できるように意識しましょう。100%理解している状態を保ち続けることは決して容易なことではないのですか、間違いなく受験勉強へ繋がります。
また、中学1年生の学習内容に不安がある場合は、ここでつまずきを解消することが大切です。塾の季節講習を利用して苦手を克服しましょう。 -
② 目標となる志望校を見つける
早めに志望校を決定できると、合格にぐんと近づきます。
具体的な目標をもつことで、勉強へのモチベーションを保つことができます。
これだ!という唯一無二の志望校が見つかれは、合格に向けて二歩・三歩近づいたこととなります。
3中学3年生から始める場合
残り少ない時間を有効に活用するために、しっかりスケジュールを組んで、それぞれの時期にやるべきことを意識して勉強を進めましょう。
-
① 春から夏休みまでにやること
部活動も引退前の大切な大会があり重要な時期となるので、部活動と勉強の両立を意識しましょう。
夏休みまでの期間は単元ごとの勉強の他に、高校入試問題を意識した基礎力を作る勉強にも取り組みましょう。習ったことを定着させるためには繰り返し復習や確認の時間が必ず必要になります。そのため早い段階で中学3年生までの学習範囲を終えられると、受験前の総復習の時間を多くとることができます。そのため、もし中学3年生からの通塾を検討しているのであれば、3月から入塾し、少しでも勉強を進めることをオススメします。 -
② 夏休みにやること
中学1・2年生の総復習を行いましょう。これまで国語、数学、英語の3科目を中心に勉強している場合は、ここに理解・社会も加えましょう。中学1・2年生の学習範囲で抜け漏れが多い場合や、苦手が多くある場合は、個別指導塾に通って自分に合ったカリキュラムに沿って指導してもらえると良いです。
また、まとまった学習時間が確保できる夏休みは適切な対策を立て、弱点強化・弱点分野の対策に真剣に取り組みましょう。この時期にどれだけ苦手分野に真剣に取り組めるかで実力が大幅UPするかどうかがかかっています。 -
③ 9〜12月にやること
秋になると、単元ごとの学習がゴールに近づき、いよいよ3年間の総復習や過去問演習に取り組む、入試対策が中心となります。これまで積み上げてきた基礎力を得点力に変えていく時期です。
-
④ 入試直前〜入試期間にやること
基本的には9月以降に行なっている入試対策を継続します。入試対策の中で自分の弱いところ、苦手分野が見えてきます。そこを確実に潰せるように学習を進めましょう。
入試日程に入ってからも今までのペースを崩さずに、いつも通りに過ごしましょう。入試期間は最もモチベーションが上がっている時期であり、実はまだまだ得点力を上げられる時期です。むしろ、1番伸びる時期といっても過言ではありません。
「戦略」と「戦術」の違いを知っている人が成功する
戦略

中長期的。全体的な方針であり、変更はしない。
どの教科を受験教科にして今の成績と比べてどの程度取り組むのかを考えること。具体的な成績の管理や目標設定を行う。
戦術

短期的。個別の方針であり時と場合によって変更もある。
各教科に関して最短・最速で成績を上げること。例として、塾に通い何のテキストを使っていつまでにどの単元をマスターするなどの計画を立てる。
目標を達成するためには、まず戦略を確定させる
大切なのは、まず戦略が確定して、その後、戦術をマスターしていくことです。
公立高校が第1志望の場合と、私立高校が第1志望の場合では、戦術が違います。
5教科か、3教科かで戦術は変わってきます。
目標を達成するためには、戦略と戦術が存在し、まず戦略を確定させることから始めなければなりません。
志望校を確定させることなしに、受験勉強を始めるのは、意味がないのです。
戦略の前に「目標」、戦術の後に「日々のやることリスト」
・目標:何処の高校を受験するのか(具体的な志望校)
・日々のやることリスト:日々の目標。戦術よりもさらに細かい計画で、明日ではなく、今日、今、やらなければならないことのリスト。
多くの人がいきなり日々のやることリストに気を取られがちですが、目標から考えて、目標→戦術→戦略→日々のやることリストと落とし込んでいきましょう。
「5教科」でいくか、「3教科」でいくかを決める
高校によっては5教科で受験する高校と、3教科で受験する高校があります。第一希望が5教科であれば5教科、第一希望が3教科であれば3教科を選択すべきです。5教科と3教科では戦略が異なります。
● 5教科の場合
メリット…問題のムラが少ない、他の教科でカバーしやすい
デメリット…3教科よりも勉強する範囲が広く、基礎力を身につけるのに時間が必要
● 3教科の場合
メリット…絞って勉強しやすい
デメリット…当日の試験問題の当たり外れに左右されやすい
受験に必要な知識をしっかりと、情報収集して対策をしていくことが、受験に必要な科目や傾向と対策をして、弱点や苦手を発見し克服することが最重要な学習方法になります。そのための効率の良い学習方法をマナビバは提案しております。
また、志望校の受験科目を調べたら、科目毎の最も効率の良い学習方法があります。その学習方法を特別に公開しておりますので、是非参考にご覧ください。
偏差値とは関係なく、憧れの高校を第一志望にする
「憧れが力を生む」という言葉があります。
憧れる力さえあれば、人はパワーを発揮することができます。
「どうしても可愛い制服が着たい」「この学校に入れば、モテモテの生活を送れる!」などと強く願っていれば、現時点の偏差値は関係ありません。偏差値よりも、志望校対策ができているかどうかで、高校受験は決まります。

高校受験は「数学」で決まる!
数学は生まれつきの頭の良し悪しではなく、積み重ねで決まる。
数学の勉強の必勝法は「抜け」をなくしていくことです。「抜け」というのは、本来知っていてもおかしくないはずなのに盲点になっていて知らない箇所のことです。例えば、小学校3年生の問題を解いた時に、100点満点中90点しか取れなかった場合、失点した10点は「抜け」だったため失点したのです。
小学生の数学に「抜け」がなくなれば中学1年生の数学では満点が取れるようになり、中学1年生の数学で「抜け」がなくなれば中学2年生の数学では満点に、中学2年生の数学で「抜け」がなくなれば中学3年生の数学では満点になるということなのです。まず小学生の問題集から見返していくのが、数学の勉強の最初の一歩となります。
このホームページを読んで“なるほど”と思ったり、“どうすれば「抜け」がなくなるのだろう”と思った方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。無料でおすすめの勉強法をプランニングいたします!
国語には「ムラ」がある
漢字問題→古文→論説文→小説の順にムラが大きくなります。
漢字は答えが一つしかなく、古文は解釈が分かれる場合もありますが、有名な古文問題は答えが確定しているのでしっかり勉強すれば満点を狙える分野です。
論説文や小説といった、記述式の問題に関しては、採点者によって「ムラ」が生じる場合があります。試験・採点者によって、採点基準が変わってしまいます。
ただし、現代文はコツさえ掴んでしまえば、学習時間をあまりかけずに高得点が可能な科目なのです。
その理由は、答えの90%は文章の中にあるからです。
「次の文章を読み、後の問題に答えなさい。」という問題を見たことはあるでしょうか?定期テストも入試問題もこの文章が基本的に読解の問題の前に書かれています。つまり「答えは文章の中に書かれていて、なんの事前知識がなくても回答が可能」であり、その解答を文章の中から探すという訓練さえ積めば大きな得点源となるのです。
「知っているか知らないか」を問う社会や理科とは違い、「考えればわかる」という思考能力を問う問題なのですが、コツさえつかめば解答を導き出せるような内容のものが一般的です。国語の問題は、問題を作成した担当者との知恵比べのような要素もありますが、基本的には、「どんな解答をさせたいか」を読み取る科目なのです。
高校受験の英語は、●●で決まる!?
英語学習をザックリとした大枠で区切ると、<英単語>、<英熟語>、<英文法>、<重要構文>、<長文読解>と分けて勉強している学校や、学習塾が一般的かと思われます。これは完全に非効率な学習方法の典型的な例で、まだ生徒たちの年齢で長時間無駄に机に向かわせるような愚行とも言えるでしょう。英単語や英熟語は文法問題や長文読解の際に一緒に覚えてしまうからです。
重要構文は、長文読解の際に出てきたら要点を抑えながら、意味を把握する訓練をしたほうがよほど実践的な重要構文の学習が可能ですし、近年の高校入試の英作文や長文読解では重要構文を理解していなければ、解答を導き出せないような問題も見受けられます。
そのような問題に対して、英単語は用法を無視した無理な日本語訳で暗記し、重要構文も同様で、ブツ切りの熟語の延長のように教わることは英語力の習得に役立つのか?入試対策と呼べるのか?それで生徒の学習時間の削減に繋がるのでしょうか?わたしは効率の良い学習をしてもらいたいと考えております。
そのコツを特別に無償でお教えしますので、是非個別指導塾マナビバへお問い合わせください!
公立高校入試科目別対策
国語~ 記述の攻略がカギ! ~
傾向1 記述式の問題が70%以上出る!
文章中の言葉を使って正確に書く必要があるので、まとめ方のポイントを身につけて確実に得点につなげましょう!設問文を丁寧に読んで答えの形を決め、本文から使えそうな部分(答えは本文の中にある)を探し、字数などを気にせずとにかく書いてみる(下書きをする)のがポイントです。
傾向2 漢字の読み書きは比較的易しめ
知識問題は行書の特徴や漢詩、手紙、辞書など、毎年異なる題材が出題されています!対策として、漢字や熟語の構成・文法・表現方法などを丁寧に確認しておこきましょう!特に漢字は同音異義語や形の似た漢字、四文字熟語、部首などに注意し、文法や敬語などもしっかりおさえておくべきです!
傾向3 発言の意図・効果が問われる
小説では登場人物の心情、文章の内容や表現に関する問題、論理的文章では語句知識、筆者の考え、内容把握などの問題が出題されます。
記述力が必要になるので、特に文章の空欄に当てはめる形の記述問題の練習を重ねましょう!
12018年度の問題構成
| 標準問題 | |||
|---|---|---|---|
| 問題番号 | 分野 | 内容 | 配点 |
| 1 | 漢字・国語知識・文法・説明的文章 | 国語知識に加え、説明的文章の読解も出た | 21点 |
| 2 | 漢字・国語知識・会話発表・作文 | 漢字に加え、会話・発表に関する問題や作文が出た | 15点 |
| 3 | 小説 | 記述の問題が多い | 15点 |
| 4 | 古典(古文) | 内容を記述する問題が出た | 9点 |
| 学校裁量問題 ※小説や説明的文章では長い記述がでることが多く、難問。配点も高めなので対策が必要! | |||
|---|---|---|---|
| 裁量1 | 漢字・国語知識・会話発表・作文 | 漢字に加え会話・発表に関する問題や作文が出た | 15点 |
| 裁量2 | 小説 | 記述の問題が多い | 15点 |
| 裁量3 | 説明的文章 | 小問数が多い | 21点 |
| 裁量4 | 古典(古文) | 内容を記述する問題が出た | 9点 |
22019年度入試予想
配点の半分は漢字と記述式の問題であり、他は書き抜きや記号選択です。記述式問題は文字数が増加傾向にあり、難易度も年々上がっております。
本番は時間配分を意識して取り組む必要があり、日頃から時間を設定して問題に取り組む練習を重ねましょう。
また、先に設問を読むことで、本文をどのような観点で読み取れば良いのかがわかり、素早く主題を把握することにつながります。漢字や文法など確実に得点できる問題から解くのもポイントの一つです。
韻文・実用文
- 韻文:表現技法、季節や句切れに注意。
- 敬語:動作の主体に注意。
- 実用文:提示された資料を丁寧に読み取る。
- 教科書の内容もしっかり理解しておきましょう。
長文
- 文学的文章:行動・会話・情景描写がどんな心情を表しているかを考えながら読みましょう。
- 説明的文章:具体例や経験などの事実を述べた部分なのか、主張や考えなどを述べた部分なのかを意識して読むのがポイント。
古典
- 歴史的かなづかいの読み方をしっかりおさえておきましょう。
- 主語や話者は省略されていることが多いので、常に意識しながら読みましょう。
- 漢文は、返り点(レ点、一二点)を確実に理解しましょう。
裁量
- 記述の攻略がカギ。演習→復習を繰り返すことで、「書く力」を確実につけましょう。
数学~ 実践的な問題演習が必要 ~
傾向1 解きやすい問題の配点が半分以上
大問1では主に、数や平方根の計算、式の計算、方程式の計算、関数や図形の基本問題が、大問2ではここ数年作図が出題されており、角の二等分線や垂線を利用する比較的取り組みやすい内容となっているので、確実に得点できるようにしておきましょう!
傾向2 解き方をこたえさせる問題が出題
年度によって分野は異なるが、途中の計算過程を書く問いが1~3題程度出題されます。類題をこなしてポイントをおさえ、簡潔に記述する練習をしておきましょう!
傾向3 関数や図形などが頻出分野!
三角形の合同条件や相似条件など、基本的な範囲での出題。慌てずに取り組むために日頃から証明を書く練習をしておきましょう!また関数や図形分野を中心に少し難しめの問題に取り組み、思考力を養おきましょう!年度によっては確率や方程式などの分野からの出題があることも。
12022年度の問題構成
| 標準問題 | |||
|---|---|---|---|
| 問題番号 | 分野 | 内容 | 配点 |
| 1 | 小問集合 | 計算問題を含む8問 | 21点 |
| 2 | 小問集合 | 確率の問題や作図問題など | 14点 |
| 3 | 資料の活用 | 資料の散らばりと代表値の問題 | 7点 |
| 4 | 関数 | 関数のグラフと図形の融合問題など | 10点 |
| 5 | 平面図形 | 図形の証明問題など | 8点 |
| 学校裁量問題 | |||
|---|---|---|---|
| 裁量1 | 標準問題2と同じ | 15点 | |
| 裁量2 | 標準問題3と同じ | 12点 | |
| 裁量3 | 標準問題4と同じ | 13点 | |
| 裁量4 | 標準問題5と同じ | 20点 | |
| 裁量5 | 数と式・関数・平面図形・空間図形 | 方程式の文章題や空間図形の問題など | 21点 |
22023年度入試予想
標準問題採用校の場合に最も重要なのは基本的な問題は確実に得点することです。中学3年間の復習をしっかりとし、分野ごとに集中的に重要項目の練習を行いましょう。
裁量問題採用校の場合については、共通問題の部分は確実に得点できるように出題傾向に慣れておきましょう。
裁量問題は比較的易しい問題から高難度問題まで織り交ぜられているので、時間配分に注意しながら解くイメージをもてる問題から取り組み、効率よく得点することが大切です。
数と式
- 標準問題採用校:正負の数や平方根の計算、文字式の表現や計算、式の値などの基本事項はしっかりおさえておくこと。
- 裁量問題採用校:計算や式の変形を利用して様々な応用問題が解答できるように対策しておきましょう。
方程式
- 単純な計算の出題は少なめ。
- 文章題:数量比較、配分、割合、速さなどの題材で、様々なパターンの立式を練習しましょう。
- 関数や図形など他の分野でも方程式を利用する問題も多いので、図形を題材にした出題も要注意。
図形
- 円や多角形の角、おうぎ形の面積、空間図形の体積・表面積や掃除を利用した長さの求め方など基本事項が大切。
- 裁量問題採用校:相似や三平方の定理を活用して長さや面積を求める練習が必須!
資料の活用
- 度数分布表、ヒストグラムなどを題材とした、相対度数や代表値に関する出題に注意。
- 確率は頻出!場合の数の求め方、基本的な確率の求め方を理解しておこう。
英語~ 基本的な文法、語彙、作文力がポイント! ~
傾向1 長文読解が大問4問中2問も出る
短い英文の読み取り、広告文や案内文などの読み取り、会話文から出題される。設問は選択式のものが多いが英問英答もあり。多様な要素を含んだ総合問題なのでまんべんなく様々なパターンに慣れておく必要あり!長文を読み始める前にざっと設問に目を通し、長文を読む際のヒントや設問で問われるポイントなどの情報を得ておこう!
傾向2 テーマについて書く英作文が出題
3年連続与えられたテーマについて書く英作文が出題されています。基本的な知識を試すものばかりであり、語彙の問題が単独で出題されているのが特徴的。基本的な語ばかりなので、教科書レベルの単語は確実に押さえておきましょう!
傾向3 難易度高めの長文と英作文が出題
裁量問題では約490語からなる長文では内容把握に関する設問、整序作文、条件作文などが出題されます。英作文は「24語以上」と条件があるので、テーマに基づいて英文を書く練習を積み重ねておきましょう!
12018年度の問題構成
| 標準問題 | |||
|---|---|---|---|
| 問題番号 | 分野 | 内容 | 配点 |
| 1 | リスニング | 文や語句を選択する問題など | 15点 |
| 2 | 語彙・文法 | 単語の穴埋め問題など | 20点 |
| 3 | 長文読解(英作文を含む) | 約60〜160語のエッセイ・作文などの読解。1文書く英作文あり。 | 12点 |
| 4 | 長文読解(英作文を含む) | 約290語の対話文読解。1文書く英作文あり。 | 13点 |
| 学校裁量問題 ※リスニングは約10分。残り35分で大問3つを解く必要があるのでスピードが大事! | |||
|---|---|---|---|
| 裁量1 | 標準問題1と同じ | 15点 | |
| 裁量2 | 標準問題3と同じ | 12点 | |
| 裁量3 | 標準問題4と同じ | 13点 | |
| 裁量4 | 長文読解・英作文 | 約490語のスピーチ文読解。24語以上書く英作文あり。 | 20点 |
22019年度入試予想
文法
- 1・2年生で習う内容の出題比率が高いので、早い時期に文法の基礎固めをすることが必須。
- (1)三単現の-s[-es]、(2)過去形などの-ed、(3)進行形や動名詞の-ingといった動詞の用法は徹底的にマスターしましょう。
- 疑問詞のある疑問文の作り方や受け答えの練習も行いましょう。
長文読解
- 本文のテーマ・話題を大まかに捉えた上で、話の流れを正確に捉えることが必須。
- 実際に色々な英文を用いて、it,that,soなどの指示語の内容を読み取る練習をしましょう。
- 速解力も身につけられると良いです。
その他
- リスニングはあらかじめイラストや選択肢から問いの内容を推測し、ポイントを絞って聞き取りましょう。
- 標準問題の小問集合は比較的易しい出題となっているので確実に得点できるようにしましょう。
社会~ 「問題→教科書→問題」の反復で8割を目指せ!! ~
傾向1 資料を読み取る問題が頻出!
地図・グラフ・統計表・年表・写真などの資料を用いた問題が多く、必要な情報を素早く読み取ることが必須。数をこなして問題に慣れ、解き方を理解することを繰り返し、必ず解けるようになりましょう!
傾向2 地理、歴史、公民を融合した問題
大問1で地理、歴史、公民の三分野融合問題が必ず出題されます。基礎的内容を重点的に問われるので必ず得点できるよう対策しましょう!
傾向3 毎年北方領土に関する問題が出る
歴史的経緯や各島の名称・位置を押さえておきましょう!
12018年度の問題構成
| 標準問題 | |||
|---|---|---|---|
| 問題番号 | 分野 | 内容 | 配点 |
| 1 | 地理・歴史・公民 | 地理・歴史・公民の基本知識を問う問題など | 21点 |
| 2 | 歴史 | 写真や統計資料を用いた問題、並べ替え問題など | 13点 |
| 3 | 公民 | グラフの読み取り、文章記述など | 13点 |
| 4 | 地理 | 地図やグラフ、統計資料の読み取り、作図問題など | 13点 |
22023年度入試予想
各分野とも基本的な出題が中心なので、問題演習を積み重ねて確実に得点できるように対策をとりましょう。また、文章記述は過去問などを利用し、指定語句を使うなどの与えられた条件に沿って解答する練習をしましょう。
地理
- 教科書で取り上げられる国や都道府県について、位置と国名・都道府県名を覚えた上で、その国や都道府県の自然・産業の特色をおさえることが重要。
- 問題を解いて時差の求め方や地形図の地図記号・等高線の見方・距離の求め方に慣れておきましょう。
- 表やグラフの読み取りも重要。
歴史
- 年代に関する問題は頻出。しっかり歴史の流れをおさえて確実に得点しましょう。
- 江戸時代中期までは時代・人物中心、幕末以降はできごと中心にまとめて要点をおさえましょう。
- 地名は必ず位置と合わせて覚えておきましょう。
公民
- 政治分野、経済分野ともに基本事項の出題多数。教科書の太線用語を中心に確実におさえましょう。
- 三権分立、国会と内閣の関係、需要と供給の関係、歳入と歳出などの図と知識を整理しておきましょう。
- また、数字がらみの項目(過半数、3分の[2]、4年・6年など)もピックアップして覚えましょう。
理科~ 実験の手順と結果をしっかり読もう! ~
傾向1 実験観察がテーマの問題が出題
いくつかの実験を組み合わせた問題が多く、複数の単元で学習したことを関連づけて考察する思考力・応用力が必要。確実に得点するために、用語の正確な知識と理解を深めましょう!
傾向2 毎年必ず作図や論述問題が出題
観察や実験の結果から考察される問題が頻出!授業や教科書で出てきた実験観察を通して、得られた結果からわかることを短くまとめられるように練習しておきましょう!
傾向3 「遺伝・細胞分裂」が出やすい!
特に「メンデルの遺伝の法則」や「植物の根の成長を調べる実験」が頻出!遺伝の規則性、実験操作の理由や根の成長の仕組み、細胞分裂の順序をおさえておくことが大切です!
12018年度の問題構成
| 標準問題 | |||
|---|---|---|---|
| 問題番号 | 分野 | 内容 | 配点 |
| 1 | 小問集合 | 18点 | |
| 2 | 地学 | 気象観測、空気中の水の変化、前線と天気の変化 | 10点 |
| 3 | 化学 | 化学変化とイオン | 11点 |
| 4 | 生物 | 血液循環、運動の仕組み | 10点 |
| 4 | 物理 | 圧力 | 11点 |
22019年度入試予想
小問集合は穴埋め形式で語句を答える問題が多く、比較的容易に得点できます。大問は全て実験または観察から出題されるため、実験や観察内容を確実に読み取り、理解し、その結果の元、考察して表現する力が必要です。
物理
- 分野をまたいで融合した問題が出題されることが多いです。
- 総合的な問題で十分に演習を重ねましょう。
化学
- 「化学変化と原子・分子」が頻出!分解、化合、酸化と還元で教科書に載っている実験は全ておさえておきましょう。
- 気体の性質、製法、捕集方法は多分やの実験と絡めて出題されることもあります。
- 実験器具の操作方法もしっかり覚えておきましょう。
生物
- それぞれの単元の基礎を確実に固め、目新しい形式の実験や観察が出題されても対応できる応用力をみにつけましょう。
地学
- 近年、単元内の比較的狭い範囲の内容を深く掘り下げる問題や、見慣れない実験や観察から出題されることが多いです。
- 基本的な知識を確実に固めましょう。